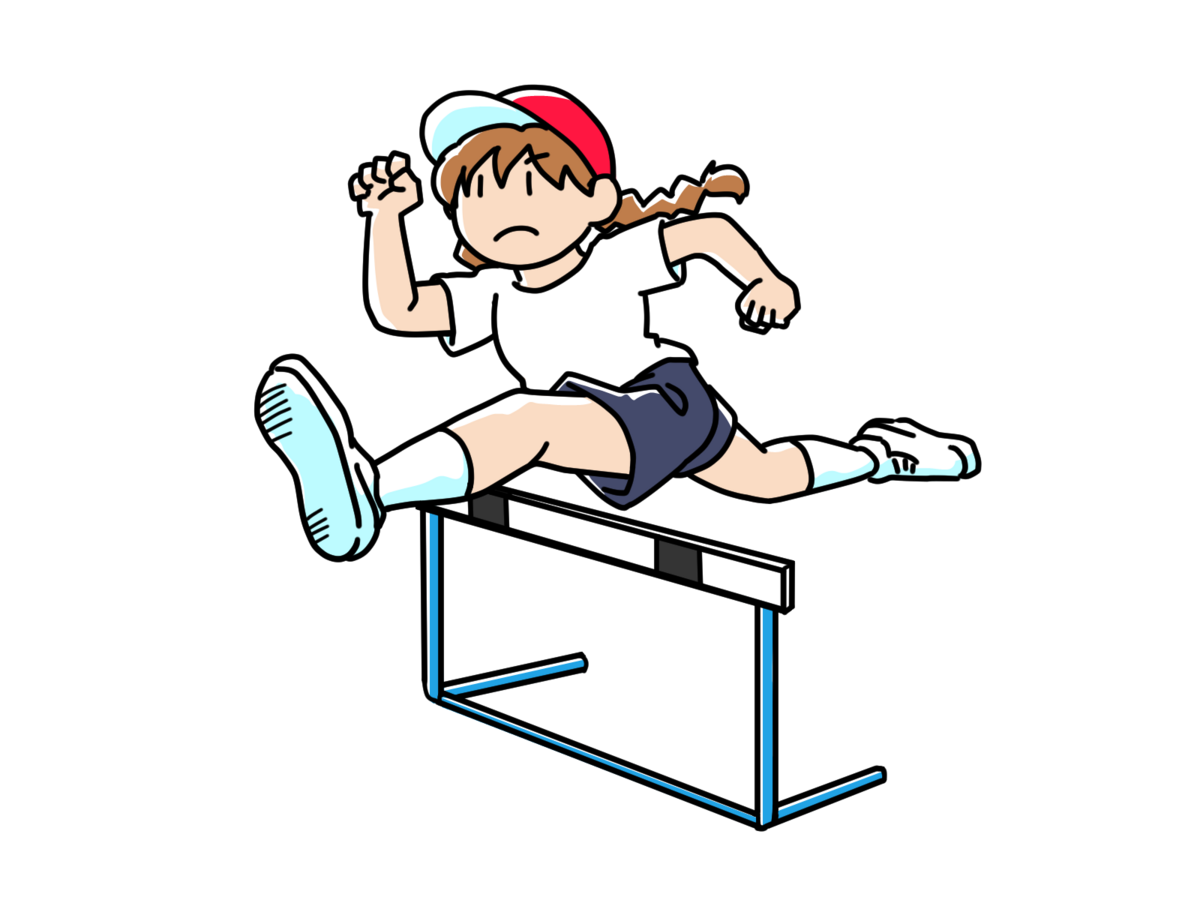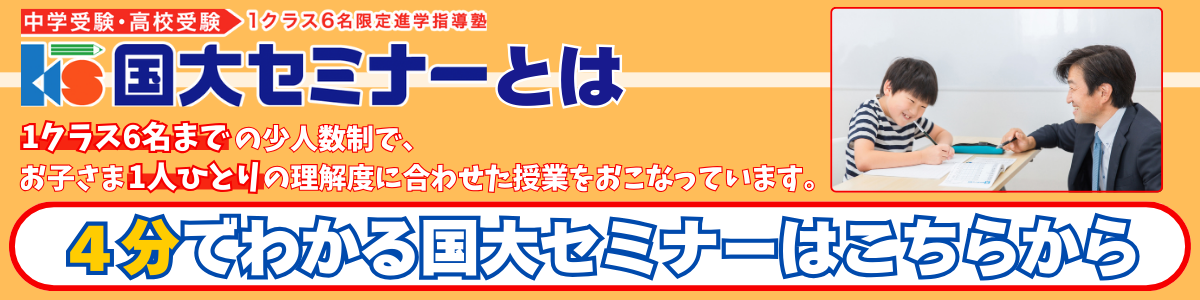「3+2.04=2.07」と答える子が急増中!小数計算の危険な落とし穴(2)
前回は、小数のたし算・ひき算の計算のつまずき、特に小数と整数の計算のつまずきについてお伝えしました。
小学4年生で小数のかけ算を学習します。ただし、小学4年生で習う小数のかけ算は小数×整数です。
例えば、3.8×4のような計算を筆算でします。
このとき、
① 小数点を考えないで、右にそろえて書く
② 整数のかけ算と同じように計算する
③ 積の小数点は、かけられる数にそろえてうつ
このように指導されます。
3.8 3.8 3.8
× 4 × 4 × 4
152 15.2
小数のたし算・ひき算で「小数点の位置を揃える」ということを学習しているため、この「小数×整数」の計算でも、小数点の位置を揃えるという感覚が適用され、比較的スムーズに理解が進むことでしょう。そのため、この段階でつまずく子供たちはあまり多くないはずです。
しかし、ここに大きな落とし穴が潜んでいます。
小学5年生になると、「小数×小数」の計算を学習します。
例えば、3.8×1.2 のような計算です。このとき、小数点の位置を決める考え方が、小学4年生で習った「かけられる数に揃える」というルールとは少し変わるのです。
この考え方の変化が、多くの子どもたちにとって大きな混乱となり、算数への苦手意識につながるきっかけとなることがあるのです。
次のステップで、この「小数×小数」でのつまずきの原因と、それを乗り越えるためのポイントについて掘り下げていきましょう。
<続く>