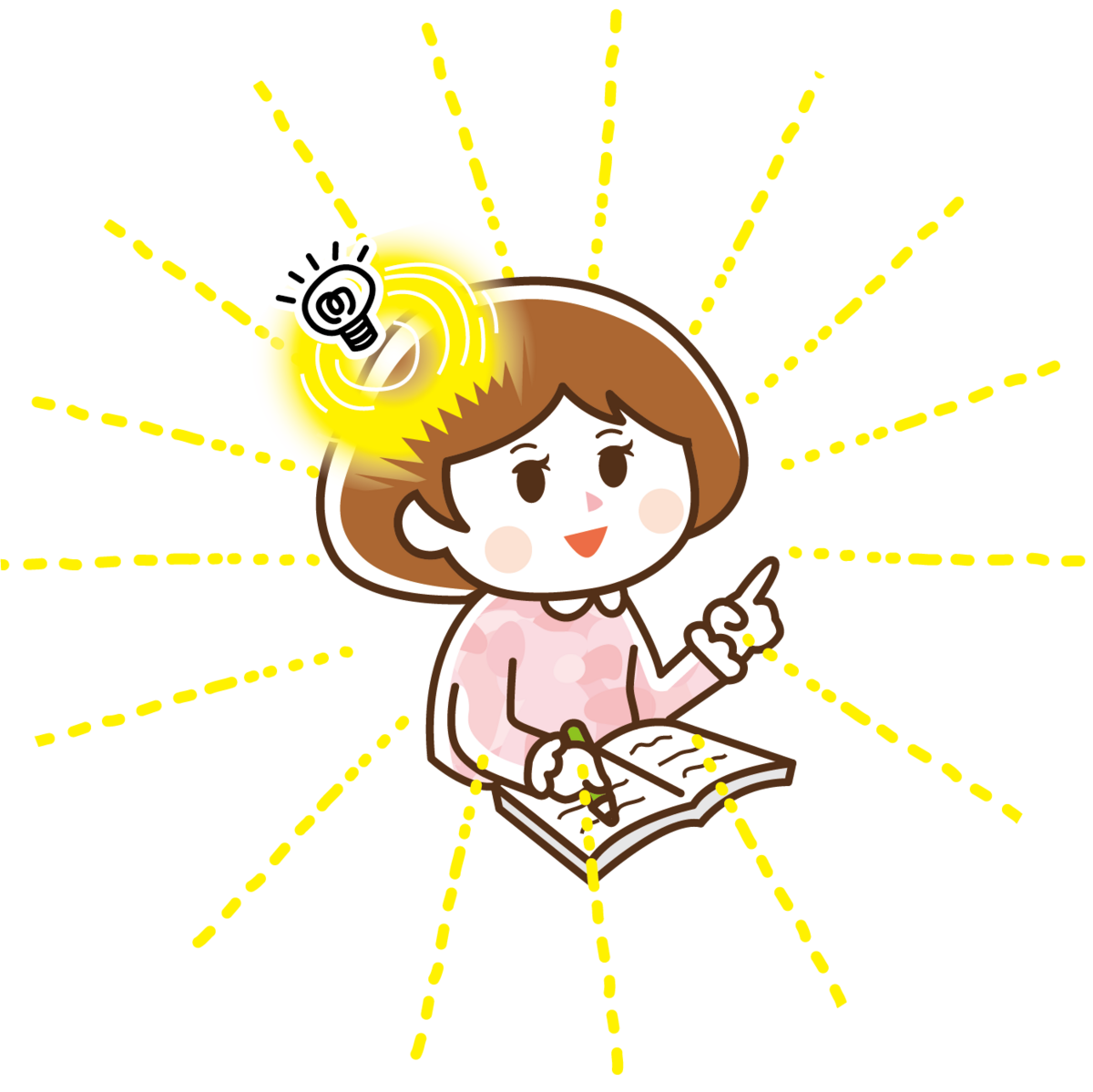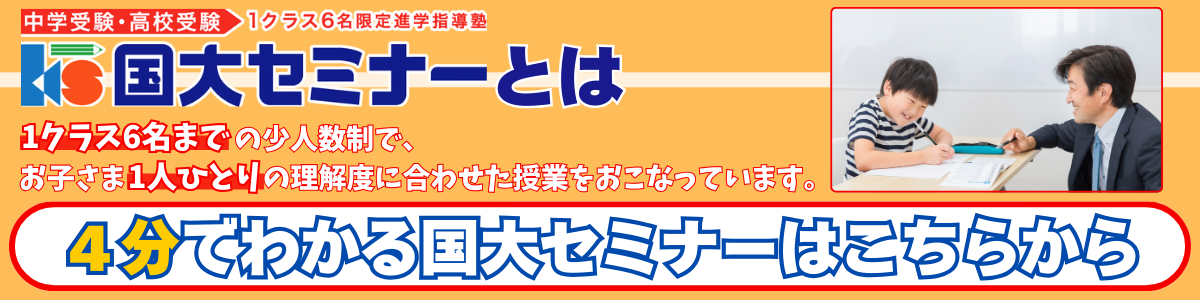コラム
2025.07.07
「3+2.04=2.07」と答える子が急増中!小数計算の危険な落とし穴(3)
小学5年生になると、いよいよ「小数×小数」の計算が登場します。
例えば、3.8×1.2 のような計算です。
ここで、子どもたちは大きな戸惑いを覚えます。なぜなら、これまでの「小数点を揃える」という考え方ではうまくいかないからです。
「小数×小数」の筆算では、以下のように指導されます。
- まず、小数点を意識せずに、右に揃えて書きます。ここまでは「小数×整数」と同じです。
- 整数のかけ算と同じように計算します。38×12 の計算で、456 という積を求めます。
- ここが重要なポイントです。積の小数点は、かけられる数とかける数の小数以下の桁数を合計した数だけ、右から数えて打つ、とルールが変わるのです。
例として、3.8×1.2 を見てみましょう。
- 3.8 は小数第一位まで(小数以下の桁数:1桁)
- 1.2 も小数第一位まで(小数以下の桁数:1桁)
この小数以下の桁数を合計すると 1+1=2 桁になります。したがって、456 の右から2桁目に小数点を打つため、答えは 4.56 となります。
筆算の例:
3.8
× 1.2
7 6
3 8
4.5 6
なぜ、ここでつまずくのでしょうか?
この「小数×小数」で多くの子どもがつまずく主な理由は、これまでの学習とのルールの違いです。
たし算・ひき算、そして「小数×整数」と、一貫して「小数点の位置を揃える」という視覚的に分かりやすいルールで計算してきたため、突然「小数以下の桁数を数える」という抽象的なルールに変わることに混乱を覚えるのです。
さらに深刻な問題として、新たなルールを覚えたことで、以前に学習したルールを混同してしまうことがあります。
そうならないためには、一つひとつのルールを確実に定着させるための訓練が不可欠なのです。
<了>